どうも、社会人生活も10年以上になりましたKYです。(@ky_rta)
社会人生活をつづけていると、いろんなひとに出会うものです。そんななかで日頃仕事をしていて思うのが、ひとそれぞれの記憶力の差。
頼まれごとをうっかり忘れてしまい、指摘をうけて「あぁぁっ」となった経験は誰しもあると思うんですよね。完璧に記憶できるひとなんてほぼいないと思いますので。
仕事に大きな影響を及ぼす重要案件などはさすがにマズいですが
でも、頻度の問題ってものがありますよね。あまりにしょっちゅう頼まれごと(たとえどんなに小さなことでも)を忘れちゃう人は、「信用度のバロメーター」がどんどん目減りしてしまいます。
そんな職場で一人は見かける(!?)忘れっぽすぎるひとの特徴について。本記事を読んでいただいている「アナタ」もそちらに属するという方のために改善方法も記載しました。
わたしも以前は「記憶力が悪すぎて絶望…」という感じだったので自戒の念を込めた記事になっています。
記憶力が悪すぎるひとの特徴
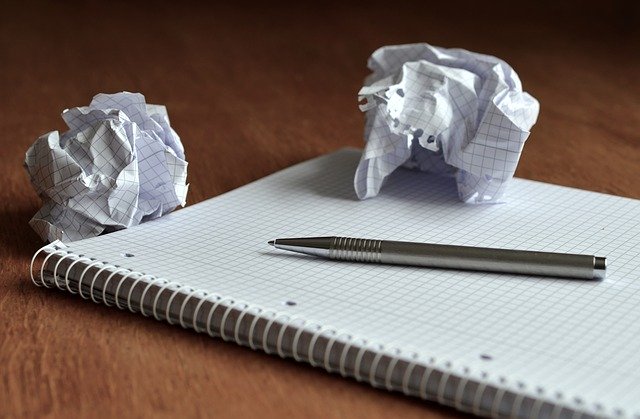
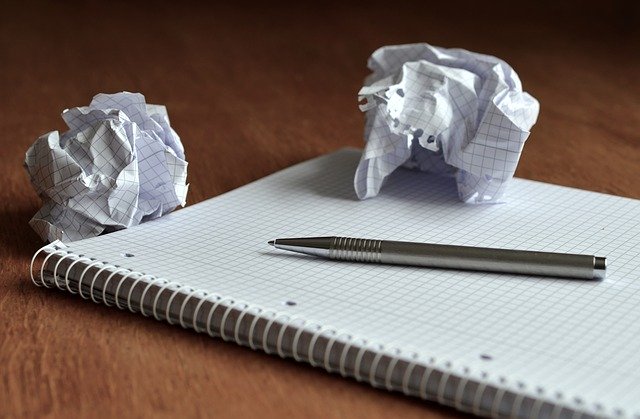
- メモを取らない、という謎の自信
- メモを取ったことをそもそも忘れる
- 忘れっぽい性格なの、と周囲にそれとなく伝えて自己保身
さて、まず記憶力の悪いひとの特徴についてですがなんとなく思い当たりませんか?わたしもとんでもなく記憶力が悪かった人間ですので気持ちはとてもわかります(笑)
わたしの場合は主に2つ目に当てはまりまして、必死にメモしても忘れてました…(絶望)
①:メモを取らない
これは覚えるための努力をおこたっているので論外ですね。それとも自分の記憶力に謎の自信があるのか…。
メモを書くのはまったくダサくないですよ!
むしろ教えている側は「ちょっと待ってください」とメモをしっかり残してもらってる姿勢のほうが安心します。
②:メモを取ったことを忘れる
普通のひとからすると信じられないかもしれませんが、記憶力悪いとあるあるなんですよ。なぜかというと、事あるごとにしょっちゅう頑張ってメモをするので「記録する媒体」が分散してしまうんですね。
「1つの手帳にだけメモしろよ!」というお声もあるかもしれませんが、たまたま手元になかったりする場合とかに電話かかってきたら、身近にあるものにメモとかしちゃうもので…。
③:忘れっぽい性格として自己保身に走る
これが1番やっかいですね。本人に改善を見込める要素が少ないからです。改善の努力が見られる場合はいくらでもサポートできますが、基本的に意志がない人間に成長を促すのは難しいと思っています。
自身の経験を踏まえた解決策です


記憶力が悪すぎた過去のわたしが、なんとか物事を覚えられるよう試してきた中で効果があり、なおかつ現在も継続しているのが以下の3点。
- 時間差で記憶を甦らせる仕掛けづくり
- チーム内で共有する(いい意味で共犯関係に持ち込む)
- メモ媒体を絞る(手帳・スマホ・PCで各1種類ずつ)
それぞれについてどのように使いこなしているのか解説です。
ちなみにわたしの場合は現代のテクノロジー(メール・チャット・グループウェア等)に助けられました。無料でつかえる便利なアプリも多いですし、使わないという手はないです。
①:時間差で記憶を甦らせる仕掛けづくり
個人的にこの仕組みづくりを自分自身のなかで確立することが1番効果があると思っています。なぜかというと人間の脳みそが記憶をするうえで有効なのが「反復」だからです。
そのために大事になってくるツールが「メール」であったり「チャットツール」です。カレンダーのリマインド機能も選択肢になりますね。
毎朝出社したらおそらく届いたメールもしくはチャットのチェックは欠かせませんよね?もはやルーティンとなっているはずです。その習慣のなかに思い出さなければいけないことを組み込むのです。
食事後に歯磨きするのと一緒の原理です。思い返せば毎日必ずやっている行動の流れがあるはず。それを活かすのが記憶するためのポイントです。
たとえ外出先であろうと、帰宅してからであろうと、思い出さなければいけないことができたらすぐに自身のメールアドレスやチャット宛にメッセージを送りましょう!翌朝出社してから悩まずともパッと思い出せるはずです。
手間を惜しまず未来の自分を助けてあげましょう!
②:チーム内で共有する(いい意味での共犯関係構築)
自分自身の記憶力に自身がない場合は、いい意味で同僚や上司を共犯関係に持ち込むのも手です。記憶しなければいけないことを報告メールに仕立て上げて、CC(カーボン・コピー)で巻き込みます。チャットでグループをつくっての報告でもよいと思います。
最悪自分が忘れてしまっても(本当は良くないですが)、誰かが覚えてて思い出させてくれればOKです。同僚や上司の記憶リソースを使わせてもらうようで申し訳ないですが、忘れてしまって迷惑をかけるよりマシですね。
副産物として報連相もクリア!
そしてなによりメールやチャットで宛先に自分を含めることにより、時間差で思い出せる仕掛けづくりとしても作用します。
③:メモ(記録)媒体を絞る
最後に基本的なところですが、メモをする場合は媒体を絞りましょう。以下のように仕事で使用する手帳・デバイスごとに1種類しか使わないと心に決めるといいと思います。
- メインで使う手帳
- スマホのメモアプリ(Google Keep)
- PCのメモアプリ(Sticky Notes)
例としてリンクを貼っているのは実際にわたしが仕事で愛用しているアプリです。めちゃくちゃ助けられています…!
現在は便利なアプリがたくさんありますから、用途に応じていろいろ使ってみたくなりますよね。選択の基準としてはシンプルで動作が軽快なのがオススメです。起動が遅いとその分メモを取るのもおっくうになってしまいます。
その点上記のGoogle Keepは起動が早いですし、クラウドベースのアプリなのでPCにも同アプリを入れると同期されます。Sticky Notesについてはデスクトップ上に常に表示させておけるアプリなので嫌でも目に付きます。
タスクを書き出して、処理するたびに削除すれば抜け漏れが激減すると思います。
なにかあれば都度メモをして、処理するたびに消していく。ゲーム感覚で取り組むのがポイントです。
記憶力改善のためには脳の働きを学ぶのがベスト
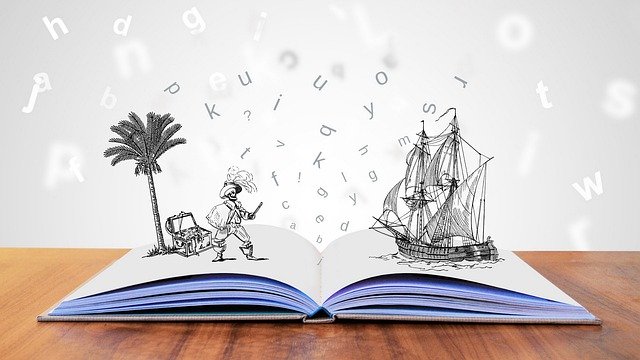
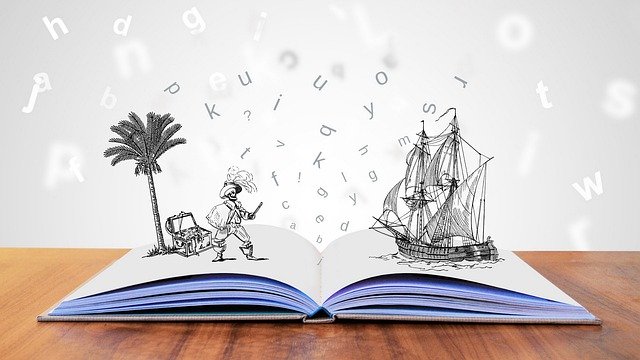
人間は練習すれば上達する生き物です。記憶力も実はスポーツなどと一緒で、正しい練習方法で学べば上達します。逆に言うと練習方法がわからずやみくもに記憶力を伸ばそうとしても、思うようにうまく行かず自己嫌悪に陥っちゃいますよね。
まずは論理的に解明されている記憶のメカニズム、脳の働きを学んでみましょう。記憶力に自信がない人ほど、素直に本と向き合ってみることをオススメします。
上記の「一流の記憶法」という本は、ハッキリいってわたしの人生を変えてくれた一冊です。
この本に出逢わなかったら今もダメダメな社会人生活を過ごしていたのかな…とゾッとします(笑)
これまで述べてきたアドバイスについては、本の中で学んだことを自分なりに咀嚼して実践していることです。自分の中でしっくりくる「記憶呼び醒ましのトリガー」を見つけることが大事なんですね。ぜひ皆さまそれぞれのトリガーが見つかることを願って本記事で締めようと思います。
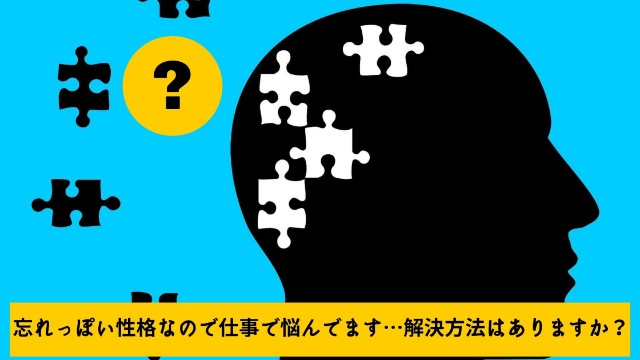



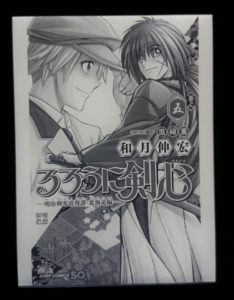






コメント